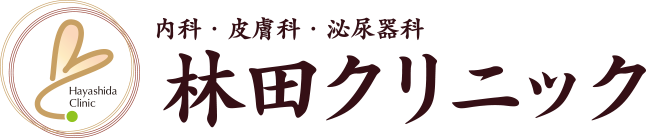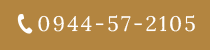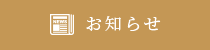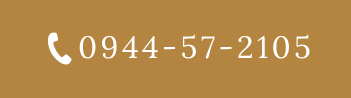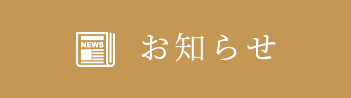一般内科
一般内科

咳や痰、鼻水、頭痛、吐き気、腹痛、下痢、めまいといった急性症状から、高血圧や糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病まで、幅広く診療しています。
「なんとなく体調が悪い」「健康診断の結果が気になる」といった場合も、ぜひお気軽にご相談ください。
また、年齢や体質のせいと諦めていた体調不良も、適切な治療で改善することがあります。
お体に関する悩みや不調がありましたら、些細なことでもお気軽にご相談ください。
発熱について
私たちの体は通常、36℃前後の平熱を保っていますが、時間帯や活動内容、測定部位によって体温は変わることがあります。
1日の体温変動は通常1℃以内です。
たとえば、普段35.5℃の方が36.8℃になると、発熱している可能性もあります。
体温は朝が低く、午後3時ごろに最も高くなるのが一般的で、午前2時頃が最も低いとされています。
正確に測定するためには、30分ほど安静にしてから体温を測るのがおすすめです。
風邪とインフルエンザ
インフルエンザによる発熱は、体がウイルスと戦っている証拠です。
症状が軽く、体力がある場合は、安静にしながら消化の良い食事を摂り、こまめに水分補給し、十分な睡眠を心がけましょう。
部屋の温度は20℃、湿度は50%を目安に保つとよいです。
基礎疾患がある方や免疫力が低下している方、また症状が強い場合は、早めに受診して適切な治療を受けることが大切です。
自己判断で市販薬を使うと、症状が悪化したり長引いたりすることがあるので、気になる症状があれば早めにご相談ください。
生活習慣病について
生活習慣病とは、日々の生活習慣が原因で発症する疾患です。
偏った食事、運動不足、喫煙、過度の飲酒、ストレスなど、望ましくない生活習慣が積み重なることで、発症リスクが高まります。
これらの習慣を改善することが、生活習慣病の予防につながります。
高血圧
血圧とは

血圧とは、血液が動脈の壁にかかる圧力のことです。
心臓が収縮する際に最も高くなる「収縮期血圧」と、心臓が拡張する際に最も低くなる「拡張期血圧」の2つがあります。
血圧計で表示される2つの数字のうち、大きい方が収縮期血圧、小さい方が拡張期血圧です。
血圧の数値は、心臓から送り出される血液の量や血管の弾力性、血管の太さによって変わります。
高血圧の目安
正常な血圧の目安は、収縮期血圧が130mmHg以下、拡張期血圧が85mmHg以下です。
ただし、血圧は時間帯や季節、運動、緊張、気温の変化などによって大きく変動します。
1回だけ基準を超えたからといって、すぐに高血圧と診断されるわけではありません。
高血圧は、長期間にわたって収縮期血圧が140mmHg以上、または拡張期血圧が90mmHg以上の状態が続くことを指します。
どちらか片方が高くても高血圧に含まれます。
血圧の測り方
診察室で測ると、緊張などで血圧が高く出ることがあるため、家庭での測定が重要です。
家庭での基準は、収縮期血圧135mmHg、拡張期血圧85mmHgです。
現在は精度の高い家庭用血圧計が手軽に入手できますので、毎日自宅で血圧を測り、記録をつけましょう。
脂質異常症(高脂血症)
脂質異常症(高脂血症)とは
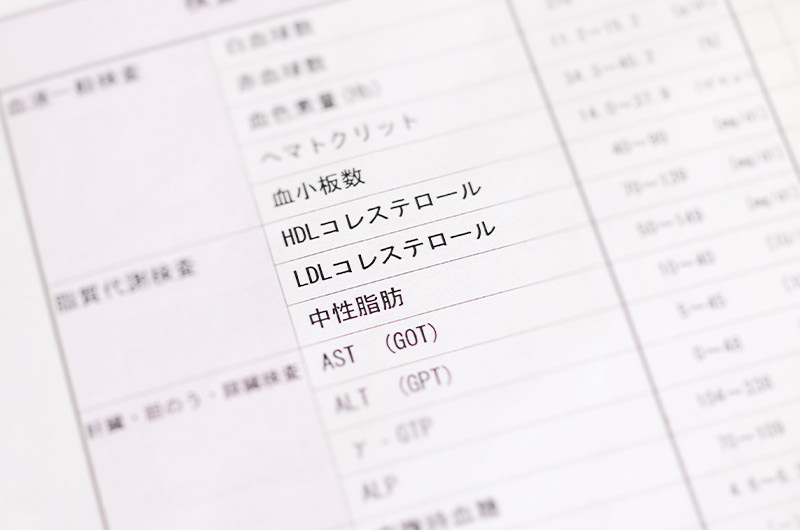
脂質異常症は生活習慣病の一つで、一般的に「高コレステロール血症」や「高脂血症」とも呼ばれます。
血液中の脂質が基準値から外れている状態が脂質異常症です。
脂質異常症の原因
「脂質異常症は脂っこいものを食べすぎた結果」と思われがちですが、それだけが原因ではありません。
以下の要因も脂質異常症を引き起こします。
- 食べすぎ
- 運動不足
- 飲酒や喫煙
- ストレス
- ホルモンの分泌異常
- 閉経後
- 薬の副作用
脂質異常症の症状と放置リスク
脂質異常症は、自覚症状がほとんどありません。
そのため、気づかないうちに動脈硬化が進行してしまうことがあります。
動脈硬化を放置すると、高血圧や脳梗塞、心筋梗塞、腎不全など、さまざまな病気を引き起こす可能性があります。
「コレステロールが少し高いだけ」と放置せず、脂質異常症と診断されたら、早めに治療を始めることが大切です。
糖尿病
糖尿病は、血糖値を下げる働きを持つインスリンというホルモンの作用が低下し、血糖値が高い状態が続く病気です。
糖尿病には大きく分けて2つのタイプがあります。
インスリンがほとんど分泌されない「1型糖尿病」と、遺伝や生活習慣(運動不足や食事内容など)が原因で起こる「2型糖尿病」です。
以前は、「糖尿病はぜいたく病」「自己管理ができない人がなる病気」といった誤解がありましたが、今では遺伝的な要因が強いことが明らかになっています。
糖尿病は、誰のせいでもありません。
長く健康に過ごすためにも、適切な治療を行いましょう。
発熱外来
発熱の原因
発熱にはさまざまな原因がありますが、その多くは感染症です。
クリニックで診察する感染症の大半はウイルス感染か細菌感染です。
まれにダニや原虫、スピロヘータによる感染もありますが、これらも見逃さないよう注意が必要です。
ウイルス感染
かぜの場合、ほとんどがウイルス感染で、悪化すると細菌感染が加わることがあります。
ウイルス感染では鼻水や痰が薄くさらっとしていますが、細菌感染では粘り気があり、黄色や黄緑色になることが多いです。
また、ウイルス感染では白血球数が下がり、細菌感染では上がることが多いため、これも鑑別の手がかりになります。
細菌感染
細菌感染には抗生物質が有効で、インフルエンザには抗ウイルス薬が使えますが、それ以外のかぜウイルスに対しては有効な薬はありません。
ウイルス感染には抗生物質は効果がないため、対症療法が中心となります。
発熱や風邪症状のある患者様へ
当院では月曜~金曜の午前10時~午後4時30時(木曜、土曜日は午後休診)に発熱外来を行っております。
37℃以上の発熱や風邪症状(のどの痛み、鼻水、咳、倦怠感、味覚がない)等の症状で診察をご希望の患者様は、来院前に必ずお電話ください。
痛風(高尿酸血症)
高尿酸血症とは、血液中の「尿酸値」が高い状態のことです。
これが続くと、関節内に尿酸の結晶ができ、激しい痛みを伴う「痛風」へと進行します。
痛風はその名の通り、「風があたるだけでも痛い」と言われるほど、非常に強い痛みを伴い、発作は数日続きます。
高尿酸血症は、以下の3つのパターンに分けられます。
- 尿酸を作りすぎるパターン
- 尿酸の排泄がうまくいかないパターン
- これらが両方合わさったパターン
高尿酸血症や痛風の多くは男性に多く見られます。
これは、女性ホルモンに尿酸の排泄を促す作用があるため、女性は高尿酸血症になりにくいからです。
女性の患者数はあまり増えていませんが、男性の患者数は年々増加しています。
心電図検査
心電図検査は、心臓の活動を記録する検査です。
狭心症、心筋梗塞、不整脈などの診断や治療に役立ちます。
エコー検査
エコー検査は、超音波を用いて体内の臓器を観察する検査です。
胃カメラや大腸カメラでは確認しにくい臓器の状態を調べたり、特定の疾患を早期に発見したりするのに役立ちます。
X線検査と違い、放射線による被ばくがないため、繰り返し検査を受けることが可能です。
特に妊婦や子供は被ばくリスクを避ける必要があるため、エコー検査が安全です。
睡眠時無呼吸検査
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、睡眠中に何度も呼吸が止まり、睡眠が妨げられる疾患です。
この繰り返される低酸素状態が、高血圧、不整脈、心不全、脳血管障害、糖尿病などの原因となることがあります。
検査は自宅で1~2晩、指先と鼻にセンサーをつける簡易な方法で行い、診断を行います。
血管年齢測定
血管年齢測定は、血管の硬さや詰まり具合を調べる検査です。
両腕と両足首の4か所に血圧計を装着し、同時に心音や心電図も測定します。
検査は約5分で終了し、動脈硬化症のスクリーニングとして役立ちます。
骨密度測定
骨密度測定は、骨粗しょう症の予防に欠かせない検査です。
骨の強さを示す指標である「骨密度」を測定し、X線を使って骨量を調べます。
特定健診、国保人間ドック健診
特定健診と国保人間ドック健診は、生活習慣病の早期発見・予防を目的とした健康診断で、それぞれ対象者や検査内容が異なります。
詳しくはこちらB型C型肝炎検査
肝炎は、肝臓の細胞に炎症が起き、細胞が壊れていく病気です。
原因はウイルスやアルコール、薬など多岐にわたりますが、特にB型肝炎ウイルスやC型肝炎ウイルスによる感染が多く、国内でも広く見られる感染症です。
肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれるように、症状がないまま病気が進行し、肝硬変や肝がんに至ることがあります。
定期的に検査を受けることで、早期発見・治療につなげましょう。